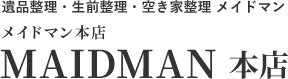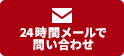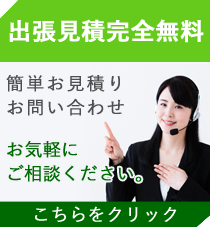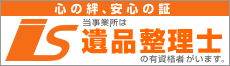公開日:2023年10月17日 更新日:2025年12月17日
 親御さんが亡くなられ、「ご実家の片付けをしなければならない」とわかっていても、気持ちの整理がつかず、どこから手をつければいいか悩まれる方もいらっしゃるかと思います。
親御さんが亡くなられ、「ご実家の片付けをしなければならない」とわかっていても、気持ちの整理がつかず、どこから手をつければいいか悩まれる方もいらっしゃるかと思います。
この記事ではご実家を片付ける際の具体的な流れや、遺品整理を進める際のポイントについてわかりやすくご紹介します。遺品整理を早めに取りかかるメリットや相続に関するトラブルを防ぐポイントも併せてご説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次

一般社団法人 認定遺品整理士認定協会
認定遺品整理士(認定 第 IS 01336号)
第二種電気工事士 愛知県知事許可 (第147439号)
1997年7月にメイドマンの運営会社、株式会社プラウドエーに入社。
2011年に認定遺品整理士の資格を取得。
現在、プラウドエーにて遺品・生前整理事業部 部長として職務にあたる。
2022年7月にて入社25年を迎える。

1. 遺品整理は相続人が行う
遺品整理は基本的に、相続人が行うことになります。相続人同士で協力して遺品整理を進めるのが理想ですが、遠方に住まわれている場合、お仕事の都合などで全員が集まれない場合もあるかと思います。そういった状況でも、まずは連絡を取り合ってスケジュール調整や作業の分担を話し合うことが大切です。
誰が・どのように作業を行うか、ご実家や財産をどのように扱うのかを決めておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。
相続放棄を考えているときは遺品整理をしない。
親御さんに借金があって相続放棄を検討されている方もいらっしゃるかもしれません。もし検討されているのであれば、遺品整理を一旦保留にしましょう。
相続放棄は、相続人になったことを知った日から3か月以内に手続きを行う必要がありますが、その間に遺品整理を行うと、「遺産を管理・相続する意思がある」とみなされ、相続放棄が認められない可能性が出てきます。
2.親が亡くなったとき、遺品整理のタイミングは?
「親が亡くなったらすぐに遺品整理を始めなければならない」と思われるかもしれませんが、必ずしも急いで取りかからなくても大丈夫です。ただし、遺産相続には期限や手続きがあるため、いつまでも先延ばしすることはできません。ここからは、親御さんと同居されていた場合・別居の場合に分けて、遺品整理のタイミングを考えてみましょう。
同居の場合
親御さんと同居されていた場合、普段暮らしている自宅の中で故人の部屋や持ち物が混在しているケースが多いため、すぐに片付けに取りかからなくても問題はありません。まずは日常的に使用しないものから少しずつ整理していくとスムーズです。
ただし、相続放棄や相続税の申告・納税などの手続きには期限があります。必要書類の整理や財産目録の作成といった作業には意外と時間がかかりますので、計画的に進めるようにしましょう。
親が一人暮らしや遠方の場合
親御さんが一人暮らしをされていた、あるいはご実家が遠方にある場合、帰省しなければならないため遺品整理はどうしても負担が大きくなります。また、住まいが持ち家か賃貸かによって、片付けを始めるタイミングや方法が変わってきます。以下では、それぞれの場合別に注意したいポイントをご紹介します。
持ち家
親御さんが一人暮らしをされていたご実家が持ち家の場合は、急いで退去しなくても問題はありません。しかし、そのまま放置してしまうと空き家となり、建物の老朽化や防犯面のリスク、雑草や害虫の繁殖などによって、近隣トラブルにつながるおそれがあります。
また、長期間管理されていない空き家は行政から指導を受けたり固定資産税が上がったりするリスクもあります。
賃貸
一方、ご実家が賃貸物件だった場合は、退去時期が決まっていることが多いため、なるべく早めに着手しましょう。退去日以降も家賃が発生するケースがあるため、片付けが長引けば長引くほど金銭的負担が増してしまいます。
また、原状回復義務が生じることもあり、退去時期が迫っている中で大掛かりな清掃や修繕が必要となると、さらに時間や費用がかかってしまうでしょう。
3.親が亡くなり遺品整理するときのポイント
ここからは、親御さんが亡くなられた後にご実家を片付けるにあたって気を付けておきたいポイントをご紹介します。手続き面から実際の仕分け方法まで、押さえるべき項目を明確にしておくことで、後々のトラブルを防ぎ、スムーズに進められるようになります。
遺言書・エンディングノートの有無をしっかり確認する
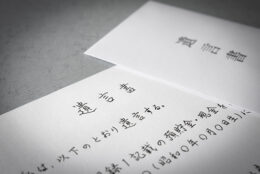
遺品整理を始める前には、遺言書やエンディングノートの有無を確認しましょう。遺言書があれば、それに従って遺産を分割する必要があります。
一方、エンディングノートは法的拘束力こそありませんが、故人の希望や想いを知るうえで重要な手がかりとなります。葬儀の希望や預貯金、SNSのアカウント情報、親族へのメッセージなど、さまざまな内容が記載されている場合がありますので、書面やデータで残されていないか探してみてください。
相続財産になるものを見つける
ご実家の中にあるさまざまな物品のうち、相続財産となり得るものは見逃さないようにしましょう。一般的には下記のようなものが相続対象として考えられます。
●プラスの財産
- ○現金、預貯金
- ○有価証券(株式、債券、ゴルフ会員権など)
- ○不動産(土地、家屋)
- ○不動産上の権利(借地権、借家権、抵当権など)
- ○一般動産(自動車、貴金属、骨董品など)
- ○損害賠償請求権
- ○知的財産権(著作権など)
- ○被相続人が受取人になっている生命保険金
など
●マイナスの財産
- ○借入金、ローン
- ○税金・医療費など未払いのもの
- ○保証債務
- ○損害賠償債務
など
マイナスの遺産が大きい場合は、先述の通り相続放棄を検討する必要があるかもしれません。相続するにせよ放棄するにせよ、手続きは複雑なので、早めに専門家へ相談すると安心です。
スケジュールを決める。
遺品整理は時間も体力も必要な作業です。特に、遠方にご実家がある場合は、交通費や滞在費もかかりますので、「いつまでに終わらせるか」スケジュールを具体的に決めておくと良いでしょう。
49日の法要のタイミングで親族が集まることが多いため、この時期に予定を合わせて話し合いをしたり、作業を分担したりすると効率的です。
遺品を買取依頼できるものとそれ以外で分ける
遺品整理では、家電や家具などの大型の不用品が出てくることも少なくありません。これらを「買取可能なもの」と「処分するもの」に分けていくとスムーズです。
特に、大きな家具や家電などを先に整理すると室内にスペースが生まれ、一気に片付いた印象になり、「頑張ろう」というモチベーションを維持しやすくなるメリットもあります。
4.自分で遺品整理するときは全体の流れを把握しておこう
「自分の手で遺品整理をやりたい」と思われる方も多いのですが、いざ実際に取りかかってみると想像以上に大変です。あらかじめスケジュールを組んでおくことで、トラブルや時間のロスを減らせます。手順や注意点については、以下の記事でも詳しくご紹介しています。
自分でできる遺品整理の進め方。業者に頼むメリットも解説
5.早めに遺品整理をした方がいい理由
「まだ気持ちの整理がつかない」「忙しくて時間が取れない」と先延ばしにしていると、思わぬトラブルや負担が増えてしまうことがあります。遺品整理を早めに行うことで、以下のようなトラブルを防げます。
財産相続に関するトラブル
財産相続は金額の大小にかかわらず、親族間で大きなトラブルに発展しがちです。後回しにしていると混乱を招き、裁判や絶縁にまで発展することもあります。
「どの財産を誰がどれだけ相続するのか」をできるだけ早く共有し、遺品の仕分けについて納得するまで話し合うことで、大きな紛争を避けることができます。
ご近所トラブル
特に一軒家の場合、放置して老朽化が進むと雑草や害虫の発生、建物の倒壊リスクなどで、近隣住民に迷惑をかけてしまうことがあります。
ご実家が空き家になる場合は早めに遺品整理を行い、建物の管理や売却・賃貸などを検討することが大切です。
部屋を早く明け渡せる
遺品整理を早めに行うことで、退去手続きや明け渡しにかかる費用を抑えられる場合があります。賃貸物件であれば、居住実態がない期間も家賃を支払う必要があります。以下の記事でも空き家に関するリスクと対策をご紹介しています。
https://maidman.net/column/68276.親が亡くなったときは親族でしっかり話し合うことが大事
親御さんが亡くなられたら、相続やご実家の片付けは避けて通れません。こうした問題は一人で抱え込むとストレスも大きく、間違いや見落としにつながりやすいです。相続人(親族)同士でしっかり話し合い、協力し合うことが、スムーズ・円満な遺品整理への近道となります。
7.愛知県名古屋市の遺品整理はメイドマンへ

愛知県名古屋市で遺品整理やご実家の片付けをご検討されている方は、ぜひメイドマンにご相談ください。1996年に名古屋市で創業し、地域密着とスピーディーな対応で厚い信頼をいただいてまいりました。
明瞭会計を徹底しており、不用品の買取も行うことで費用を抑えられる可能性があります。ご遺族の方と故人の思いを尊重し、丁寧な対応を。遺品整理はもちろん、お部屋の清掃や植栽の剪定、引っ越しのお手伝いなど幅広くご実家の整理をお手伝いいたします。