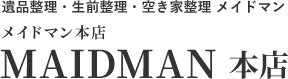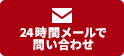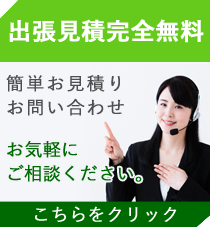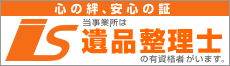公開日:2025年04月09日 更新日:2025年12月17日
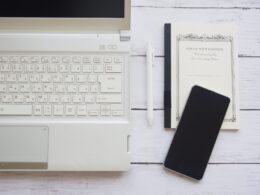
故人のスマートフォンに着信やメッセージ、通知が大量に届いている、パソコンにデータが膨大に入っていて消していいものなのかがわからない、高額なインターネットサービスの利用料の請求が来た……パソコンやスマートフォンの普及によって、最近このような事例が増えてきています。
この記事ではデジタル遺品整理に悩むご遺族の方のために、確認ポイントから注意点、生前に備える方法までをまとめました。お読みいただくことで、デジタル遺品の扱い方や整理の方法がわかりますので、ぜひ参考にしてください。
目次
1.デジタル遺品とは
デジタル遺品とは、故人がスマホやパソコン、クラウドシステムなどに残したデータやアカウント、そしてそれらを操作する端末や記憶媒体自体を指します。写真やメール、連絡先といったデータはもちろん、ネット銀行やキャッシュレス決済の残高、サブスクの契約情報まで幅広いため、金銭面・個人情報面のリスクが高い遺品といえます。
2.デジタル遺品の種類
デジタル遺品は「オンライン上のもの」と「オフライン上のもの」の大きく2種類に分けられ、それぞれ以下のようなものが挙げられます。
オンライン上のもの
- ネット銀行・証券口座
- クレジットカード連携のキャッシュレス決済
- SNS、ブログ、動画配信サービス
- クラウドストレージ(Googleドライブ・iCloudなど)
- サブスクリプション(音楽・動画・ソフトウェア)
オフライン上のもの
- スマホ・タブレット・PC・外付けHDD
- SDカード・USBメモリ
- デジタルカメラ内のメモリ
- NAS(家庭用サーバー)など
3.デジタル遺品整理でやること

デジタル遺品整理は、「アクセスできる状態を確保する」「金銭に直結するものから止める」「思い出やデータを保全する」という大きな流れがあります。これを意識して進めていきましょう。
端末のロック解除
最初の壁は端末やサイトのパスワードや指紋・顔認証などをクリアすることです。場合によってはパスワード情報が端末に保存されていることもあります。故人が遺言書やエンディングノートに控えている場合もあるため、必ず探しましょう。
どうしても解除できない場合はメーカーやキャリアに相談するか、専門業者に依頼する方法がありますが、実際に解除できないことが多いのも実情です。
優先順位の高いデジタル遺品
特にネット銀行・証券口座、電子マネー・キャッシュレス決済残高、クレジットカード連携のサブスク、有料クラウドストレージなどは、放置すると自動引き落としや残高失効のおそれがあります。公式サイトで「死亡による解約」手続きを確認し、早めに停止しましょう。
SNSアカウントの削除
FacebookやInstagram、X(旧Twitter)などは遺族からの申請で削除・追悼化が可能です。追悼化すれば、SNSのフォロワーにアカウントの所有者が亡くなったことを知らせることができます。申請には死亡証明書類が必要になるため、手元に準備しておくとスムーズです。
端末内の必要なデータの移動
写真・動画は家族の思い出や遺影に、連絡先はお通夜や葬儀の案内に使える可能性があります。外付けHDDやクラウドへバックアップし、関係者が閲覧できる形で保存されるのがおすすめです。
通信契約の解除
キャリアによっては解約時に端末返却が必要なプランや、電話番号に紐づく決済サービスがあります。データ移行・SNS解約などが終わってから解約手続きを行うと安心です。
4.デジタル遺品を整理するとき注意すること

作業を急ぐあまり、思わぬトラブルが発生するおそれがあります。以下のポイントに注意しながら進めていきましょう。
パスワードを適当に打ち込まない
iPhoneは10回連続で失敗すると初期化されるという仕組みになっています。Androidでも一定回数でロックアウトされる機種があります。パスワードがわからない場合は憶測で無闇に入力せず、手掛かりを探すか専門家に相談しましょう。
相続人の同意を得る
デジタル機器も法的には遺産という扱いになります。勝手に中身を削除したり売却したりすると相続トラブルの火種になりますので、必ず相続人全員でどのように扱うのか方針を決めましょう。
整理し終わった機器は初期化する
故人の機器から情報が漏えいするおそれもあります。処分・売却する端末は工場出荷状態へ初期化し、SDカードやSIMカードも物理的に破壊して個人情報漏えいを防ぎましょう。
5.デジタル遺品は生前整理しておくことが大切
スマートフォン等のロックの解除は、専門業者でも難易度が高く、解除できないことも多いです。
ですが、突然の事故や病気は誰にでも起こり得ます。元気なうちから「デジタルの終活」を進めておくと、家族の負担を大幅に減らせます。溜まったデータの整理や不要なWebサービスの解約なども進めておきましょう。
本体のパスコードを家族が探せるようにしておく
パスワードやIDなどのログイン情報は、メモ帳や手帳などに控えておきましょう。本人だけが分かり、エンディングノートにその旨を記載すればご家族も探し出せます。合言葉やヒントを書いておくのも有効です。
iPhoneはデジタル遺産機能あり
iOS15.2以降は「デジタル遺産プログラム(Legacy Contact)」で信頼できる連絡先を登録し、仮に所有者が亡くなった場合は、登録者が代わりに操作することができます。登録者は専用アクセスキーと死亡証明書を提出することでiCloudデータを取得可能です。
契約中のアカウントやパスワードを一覧にまとめる
エンディングノートやクラウドメモにサービス名・ID・パスワードを一覧化しましょう。これによって、ご家族の負担が大幅に軽減できます。エンディングノートの書き方は「エンディングノートのデジタル資産欄とは?(https://maidman.net/column/7079)」で詳しくご紹介しています。
見られたくないものはツールを使用するのも◎
なかには絶対に漏らしてはいけない重要な情報、あるいはご家族にも見せられないデータもあるかもしれません。PC内の特定フォルダを自動削除できるフリーソフトを活用すれば、万一のときにプライバシーを守れます。
6.まとめ
デジタル遺品はオンライン(情報やデータなど)とオフライン(端末など)という大きく2つに分けられ、両方を整理することが重要です。最優先は「端末ロック解除」と「金銭に関わるサービスの停止」です。SNSアカウントの削除、写真のバックアップ、通信解約などの作業を終えたら端末を初期化して処分や売却をしましょう。
生前にパスコードやアカウント一覧を残し、iPhoneならLegacy Contactを設定することで、ご家族の負担を軽減することができます。デジタル遺品整理が自力で難しいと感じられた場合やロック解除ができない場合は、専門家に相談してみましょう。ですが、業者に依頼してもロック解除ができない場合も多くあります。もし依頼をする場合は、費用面も含め慎重に検討した方よいでしょう。
7.愛知県名古屋市の遺品整理はメイドマンへ

デジタル遺品整理で特に重要なのはパスワード関連の情報となります。スマートフォンのログインパスワードは、エンディングノートなどに記載しておきましょう。生前整理を行うときのお悩みは、私たちにご相談ください。
メイドマンは1996年の創業以来、名古屋市を中心に皆様の遺品整理・生前整理をお手伝いしてきました。明朗会計・秘密厳守で安心です。デジタル、現物問わず、遺品整理でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。